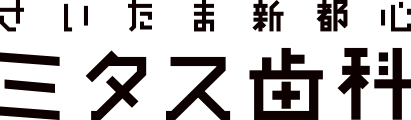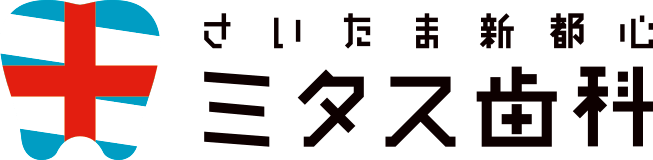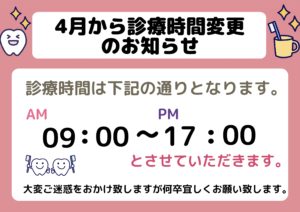さいたま新都心駅近くにある歯医者 さいたま新都心ミタス歯科 院長の大島です。私は日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医を取得しております。当院では特にインプラント治療に力を入れています。
インプラント治療は、自然な歯と同じような咬みごたえや審美性に優れるなど、多くの利点を持つ補綴(ほてつ)治療です。
しかし、全てがメリットだけとは限らないのです。今回は、インプラント治療におけるリスク、特にインプラント周囲炎について詳しくご説明します。
・インプラント周囲炎とは何でしょうか?
インプラントの材料は人工物なので、虫歯にはなりません。しかし、インプラントが埋め込まれている歯茎は生体のため、以下のようなプロセスでインプラント周囲炎が発生します。
まず、食べ物の残りカスやプラークなどがインプラントと歯茎の間に溜まると、歯周病菌が増殖します。そして、歯周病と同じように、インプラントの周囲のあごの骨が破壊されます
結果として、インプラントや周囲の歯が自然に落ちることがあります
・インプラント周囲炎の症状
歯茎から血や膿が出始め、放置すると、どんなに正確に埋入できているインプラントでもぐらつきます。最終的には抜け落ちる可能性があります。
インプラント周囲炎の症状は歯周病に似ていますが、インプラント周囲炎は歯周病よりも厄介な特徴がいくつもあります。
インプラント周囲炎は歯周病に比べて以下のリスクがあります。
痛みが出にくく、発見が難しい
歯茎の腫れが少なく、発見が難しい
出血が少ない
歯茎ではなく、骨にも急激に炎症が発生する
症状の進行が早い
インプラント周囲炎は自覚症状が少ないため、罹患に気づかない患者さんも多いのです。気づいたときには症状がかなり進行してしまうこともあります。これを防ぐためには、定期的にかかりつけの歯科医院に通い、メンテナンスを受けることが重要です。
・なぜインプラント周囲炎が増加しているのか?
ヨーロッパ歯周病学会のレポートによれば、インプラント周囲炎の発症率はインプラント治療を受けた患者さんの28〜54%と言われています。これは、かなり高い確率でインプラント周囲炎が発生していることを示しています。
では、なぜインプラント周囲炎が増えているのでしょうか?ここで重要なのが、インプラントの成功を判断する基準です。
インプラント周囲炎が発症しても、抜けていなければ成功とする基準を「生存率(サバイバルレート)」と言います。一方で、インプラント周囲炎だけでなく、周囲の骨や歯茎などが健康状態にある場合に初めて成功とする基準を「成功率(サクセスレート)」と言います。
どちらの基準を採用するかは各歯科医院の歯科医師の判断に委ねられていますが、前者の基準を採用し、実績としてうたっているところも実際には存在します。患者さんの健康を最優先する視点からは後者の方が望ましいと言えるでしょう。
良質な歯科医院の歯科医師とは、メリットとデメリットを明確に説明し、患者さんが納得した上で治療を行うものです。ホームページなどに掲載されている実績やキャッチフレーズだけでは、クリニックの良し悪しを判断するのは難しいです。
・まとめ
インプラント治療において重要なのは、歯科医師の技術力やクリニックの設備です。また、インプラント周囲炎などから患者さんを永く守るサポート体制が必要です。
インプラント治療を考えている方は、カウンセリングを行っているクリニックに訪れ、直接医師と話すことをおすすめします。さらに、将来的なメンテナンスも考えて、通いやすい立地のクリニックを選ぶことも重要です。
さいたま新都心ミタス歯科では、患者様が安心してインプラント治療を受けられるよう、安全性に重きを置いて治療を行っています。これまでに多数の症例を扱ってきた実績もございますので、治療方法や費用についてのご相談はお気軽にお問合せ下さい。
ミタス歯科の無料インプラント相談について
https://mitasushika.com/implantconsul/
ミタス歯科の無料インプラント症例について
https://mitasushika.com/medical/implant/case/
さいたま新都心ミタス歯科
日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医
院長 大島正充